▼ エドワーズ
- エドワード・エヴェン・エドワーズ
- 古書店店主
- 濃いめの金髪にライムグリーンの瞳
- 初登場時36歳、バツイチ。若い頃に一度結婚したが双方の仕事が忙しすぎて別れた。子供はなし。
- 通称EEE(トリプルE)
- 元サンフランシスコ市警の内勤巡査。ディフの始末書を何枚も処理し、レオンも事務手続きでお世話になった人。
- 穏やかで丁寧な物腰の奥に強い意志を秘めた英国紳士。幼い頃はイギリスで育ち、両親とともにアメリカに移住した。
- 2003年に父親が亡くなり、古書店と猫を受け継いだ。そのため警察は退職。
- 愛猫はリズ。
- リズの子供のうちの一匹が、オティアにひきとられた。
- 登場作品:【ex4】猫と話す本屋他

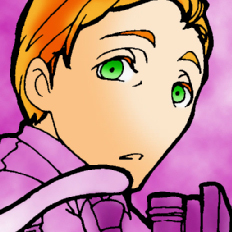
※月梨さん画「猫にたかられる本屋」

▼ 【ex4-4-2】そして結婚式で2
「この婚姻に異議ある者は申し出よ、さもなくば…………………………永遠に黙秘するように」
ジーノ氏の堂々たる執行で滞りなく式は終わり、口笛と喝さいの中、新郎新婦の『初めての共同作業』も無事終了した。
「な、何をっ、ディフっ?」
「暴れるなよ……レオン。バランスが崩れる」
「う……うん」
「しっかりつかまってろ」
レオンを抱き上げ、ハート形に切り抜いた布を通り抜けるマックスの幸せそうな表情に心が和んだ。
「お待たせいたしました。お食事の準備が整いましてございます。皆様、どうぞ中へ」
テーブルに並ぶ料理を見ながら、ああ、エビだ。これはリズの好物なんだけどな。さすがに持ち帰る訳には行かない……なんてことを考えていたら、にゅっとエリックが手を伸ばし、小エビのカクテルをまとめてごっそりと取って行った。どうやら好物らしい。
黙々とフォークを操り、エビを口に運ぶ姿を見守った。
大丈夫だ。あれだけ食欲があるのなら、立ち直るのも早いだろう。
広間の前方ではアメリカの伝統にのっとり、レオンとマックスが互いにウェディングケーキを食べさせている。行儀良くフォークを使って。
自分の時は手で直接だったが……。
今思うとあれは、新郎新婦の(主に新婦の)『はしたない姿』を客にお見せするのも余興のうちだったのだろうな。
小さくため息をついていると、肩をぽんっと叩かれた。振り向くと、キルトをまとい、バグパイプを肩にかけた『本物のスコットランド男』が立っていた。
「どうした、エドワーズ」
「マクダネル警部補。お久しぶりです」
「三年ぶりかな。元気にやっとるか?」
「はい、おかげさまで」
「うむ。ちゃんと日光にも当たっているし飯も食っとるようだな……たまには署にも顔出せよ?」
「ありがとうございます」
「退職して以来EEEの姿を見たことがない、もしや修道院に入ったか、なんてまことしやかなウワサが流れてるくらいだからな」
修道院か。似た様なものかもしれない。
※ ※ ※ ※
パーティーの間中、何となくサリーの姿を探していた。
しかしタキシードをまとった彼女も、その連れの桜の着物の従姉の姿もどこかにかき消えたように見当たらない。
もう、帰ってしまったのだろうか……。
自分も、そろそろ帰った方がいいのだろうか。
目の前では新郎新婦が手に手をとって踊っている。男同士でいったいどちらがリードするのかと少し興味をそそられたが、どうやらマックスがリードしているようだ。
考えてみれば彼はしょっちゅう女性とデートしていた。エスコートもダンスのリードも慣れているのだろう。
二ヶ月ごとに違う女性と歩いているので署内ではよほどの女好きに違いないとウワサされていたが、エドワーズは何となく違うと感じていた。
一時期、自分と同じ部署の女性職員と付き合っていたのを知っていた。仕事帰りによく迎えに来ていたのだが、ある時を境にぱったりと来なくなった。
バツイチ男への気安さからか、彼女は仕事の合間に何気なく話してくれたものだ。
『あたしにとっての一番はマックスだったんだけどね。彼にとっての一番は……あたしじゃなかったの。だから、さよならねって』
今ならわかる。
マックスにとっての一番は、あの頃からレオンだったのだ。自覚の有る無しは定かではないが。
……いや、おそらく彼自身も気づいてなかったのだろう。己の本心を隠したまま他の女性と付き合えるほど、ディフォレスト・マクラウドは器用な男ではない。
しばし過ぎし日の記憶に思いをはせ、再び現在に意識を戻すと……サリーが居た。いつ戻ってきたのだろう?
少し離れた所で友人達と楽しげに話すヨーコの背を所在なげに眺めている。
同じ年ごろの女性とは言え、やはり出身校や年代が違うと仲間に入るのは気が引けるのだろうか。
そう言えばサンフランシスコにはまだあまり友人がいないと言っていた。マックスも今日は忙しく、なかなか話すチャンスはないはずだ。
彼女にとって少しでも親しい人間がいるとしたら、それは自分なのではないか?
エスコート、とまでは行かないにしろ、話し相手ぐらいにはなって然るべきだろう……。
そんなことを考えている間に、サリーとの距離はだいぶ近くなっていた。正直なもので、いろいろ思索を巡らせる間に足は既に彼女の方に向かっていたらしい。
「一曲踊っていただけますか、Miss?」
……しまった、先を越された。素早いな、マクダネル警部補。
「ごめんなさい……俺、MissじゃなくてMr.なんです」
………………………………………………………。
………………………………。
……………。
………。
…。
(えっ?)
「おお。これは失敬。てっきりMissヨーコの妹さんとばかり」
「よく言われますけど……彼女とはイトコ同士なんです」
そうか。
よく言われることなんだ。
うん、確かにそっくりだったし自分もそう思っていた。
思っていたのだが……………。
(口に出さなくて良かった)
己の社交性の低さを、この時ばかりは神に感謝した。
なるほど、男性だったのか。彼女じゃなくて、彼だったんだ。それなら着物ではなく、タキシードを着ているのもうなずける。
(………いかんな。頭がくらくらしてきた)
新鮮な空気を求めてよろよろとテラスに出た。
「よう、エドワーズじゃないか」
「………やあ、ワルター、ネルソン」
「わう」
「うっふ」
「やあ、ヒューイにデューイ。元気そうだね」
二頭のシェパードはそれぞれハンドラーの足元に座り、ばったんばったんと尻尾を振っている。えらく機嫌がいい。
「久しぶりだな」
「うん、今日はよく言われるね」
急にヒューイとデューイがぴん、と耳を立て、立ち上がった。尻尾が高速でぶんぶん揺れる。ほとんど残像しか見えない。
「ヒューイ! デューイ!」
サリー先生だった。
「こんにちは、先生」
「いつもお世話になってます」
「……彼らの主治医もサリー先生だったんですか」
「はい」
二頭の巨大なシェパードにまとわりつかれながら、サリー先生はにこにこしている。
その笑顔を見ていて、ふっと。
頭の中で迷子になっていたパズルの1ピースが然るべき位置にかちっとはまったような心地がした。
男性だろうと、女性だろうと、彼が美しいことに変わりはないではないか。
会場の中では、ダンスを終えたレオンとマックスが幸せそうに寄り添い、手を握り合っている。
そろそろ、自分もサンフランシスコの流儀を取り入れてもいい頃なのかもしれない。
……うん、そうだ。
確かに彼はきれいだ。
次へ→【ex4-5】猫と話す本屋




